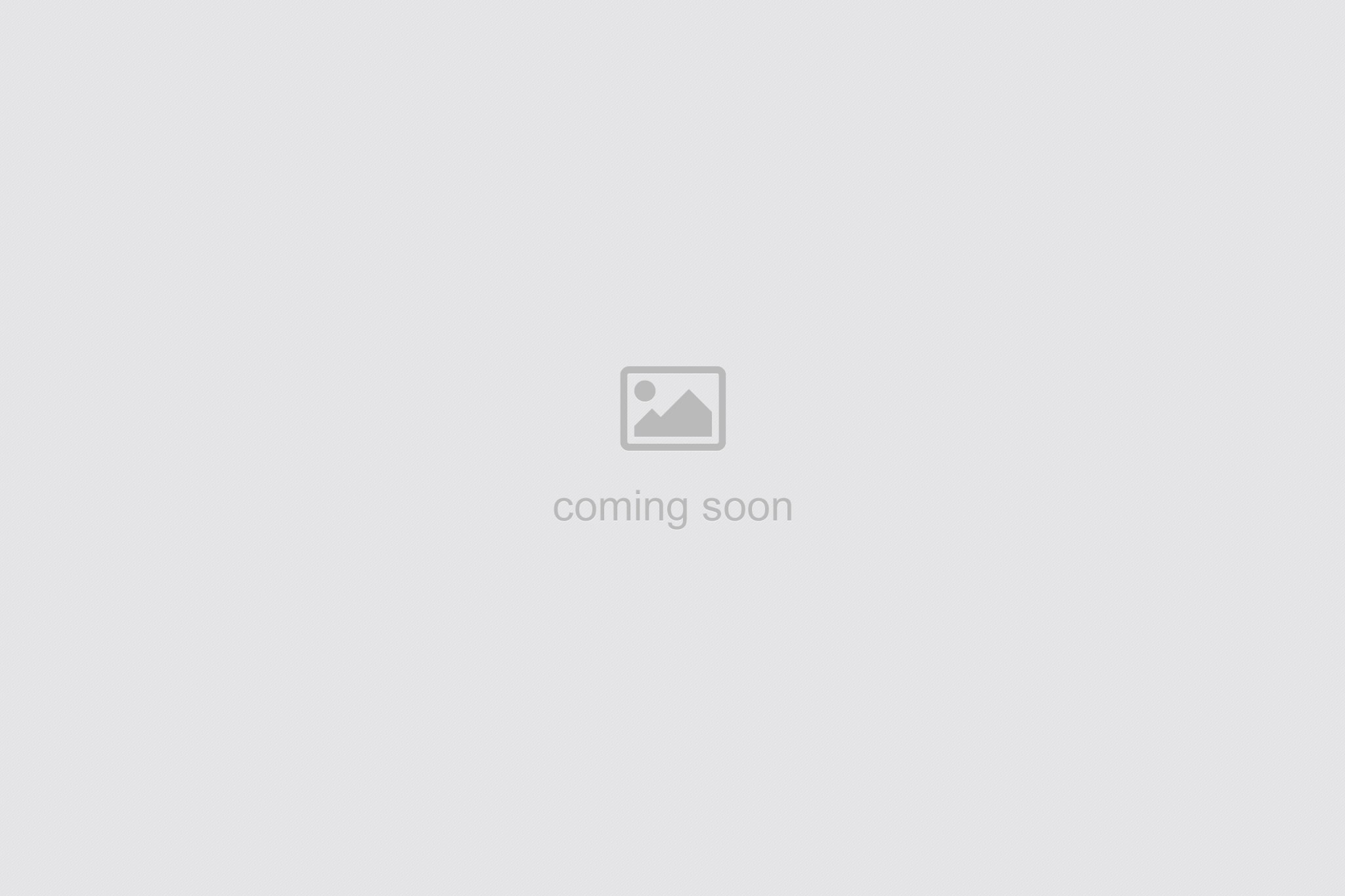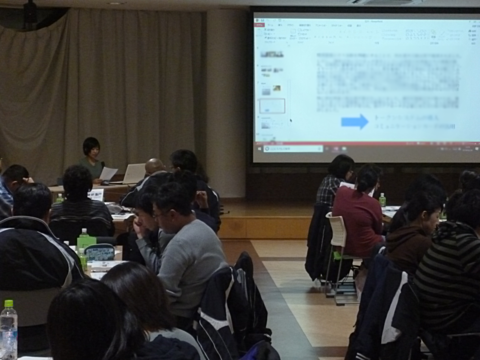研修会など
職員研修会
家族合同研修会「親亡き後を見据えて」
2019-10-26
令和元年10月26日、おんべつ学園三階集会室にて「親亡き後を見据えて」というテーマで開催され、ご家族、ご本人、職員など130人が参加されました。本別つつじの園理事長の新津和也氏より「親の思い」という演題でご講演いただきました。一般企業から福祉職に転職され、現在は北海道自閉症協会の副会長も務められています。自閉症の息子さんとの暮らしの中でのエピソードを通して、困りごとや苦労の中にも幸せを感じていること、息子さんへの愛情がとても伝わるお話でした。自分亡きあとを誰に託すのか、信頼できる人や事業所を見つけることが大事であること、特に在宅生活をされている方は暮らしの場をどうするか、年金をはじめお金はどうなるのか、仕事や活動の場はどうなるのか、現在考えうる選択肢を提示しながら説明されました。一方で施設や行政に対して障害を正しく理解して支援してほしい、何より本人や親を支える存在であってほしいとの要望があり、多くの参加者が共感されたと思います。
障がい福祉分野における親亡き後の課題は、これまで様々なメディアで取り上げられ、これをテーマにした研修会も全国各地で開催されております。今回の講演で改めて様々な問題提起をして頂きました。漠然と不安を抱えていた親御さんも多いことと思いますが、いざその時が来る前に親として、或いは支援者として、今何をすべきかを具体的に考えるきっかけになったのではないかと感じています。
研修会「自閉症の理解と支援」
2019-03-23
法人内研修とし、平成31年3月23日に、川崎医療福祉大学 准教授 諏訪敏明氏を招き、「自閉症の理解と支援」という内容で講演をして頂きました。
先生のお話として、自閉症の方を理解しようとするのに大事なのは、行動特徴を見る事である。ただ、彼らの行動特徴はしばしば大多数の人とはちょっと違う行動をする事がある。変わった行動や、指示を聞いているかどうか分からない、楽しそうなのか、本当に面白いのかも分からない。ただ、気を付けて頂きたいのは、それをすぐ直すだとか変えることではなく、実は、それが自閉症だからという事、そこを大事にして欲しい。
なぜ彼らがそのような行動をするのか?実は自閉症を診断する行動特徴は診断が初めてされた1940年代と自閉症の方の行動特徴は変わっていない。
ただその理由はどこに求めるのかという事が昔と現在では随分変わってきた。1990年代は知的障害を伴う自閉症は全体の90パーセントを占めていたが現在では、知的障害を伴う自閉症は40%、知的障害を伴わない自閉症は60%である。
その為、支援の質や内容は当然変化する。自閉症の方をどう理解していくのか。行動面の症状として、どうして起きるのか、それは自閉症の学習のスタイルの違いから生まれてくる。100の情報が提供されたとき、興味関心の強い事であれば150理解する事もあるが、関心がなければ0にしかならない事もある。100の情報をどう頭で理解し考えているのかという事に非常に特徴を持っている。自閉症の研究の中では、彼らの脳の構造、機能が違うという事が分かってきている。脳が違うわけだから当然働き方も違う、その働き方が違う部分を、学習スタイルと呼び、学習スタイルに違いのある方という捉え。だからこそ、その行動面の症状をうまくコントロールしたいのであれば、行動面だけに目を向けるのではなく、学習スタイルの違いに働きかけないと彼らの実感に落ちない。その為、そこに働きかけて支援する事で、彼らの行動が変わってくるのではないかと考える。
ただその理由はどこに求めるのかという事が昔と現在では随分変わってきた。1990年代は知的障害を伴う自閉症は全体の90パーセントを占めていたが現在では、知的障害を伴う自閉症は40%、知的障害を伴わない自閉症は60%である。
その為、支援の質や内容は当然変化する。自閉症の方をどう理解していくのか。行動面の症状として、どうして起きるのか、それは自閉症の学習のスタイルの違いから生まれてくる。100の情報が提供されたとき、興味関心の強い事であれば150理解する事もあるが、関心がなければ0にしかならない事もある。100の情報をどう頭で理解し考えているのかという事に非常に特徴を持っている。自閉症の研究の中では、彼らの脳の構造、機能が違うという事が分かってきている。脳が違うわけだから当然働き方も違う、その働き方が違う部分を、学習スタイルと呼び、学習スタイルに違いのある方という捉え。だからこそ、その行動面の症状をうまくコントロールしたいのであれば、行動面だけに目を向けるのではなく、学習スタイルの違いに働きかけないと彼らの実感に落ちない。その為、そこに働きかけて支援する事で、彼らの行動が変わってくるのではないかと考える。
「自閉症のままで、自閉症らしく」、生きられる。そういう場所、環境をどう提供するのか。ただ、それは本人たちがしたいようにさせておくという意味ではなく、彼らをどうシチュエーションじゃない人達が、大多数で暮らしている世の中と繋げていくのか、その為には、自閉症の文化、ここでの自閉症の文化とは学習スタイルと事を指すが、しっかり彼ら側から物事がみられるように考えて貰えたらと思います、という言葉でお話を閉められていました。
その後、各事業所から4つの事例を発表し、取り組みに関し先生より助言を頂いています。その中で、毎日同じ衣類を着るという行動の方に対し、「今日はこの衣類を着用する」という事を視覚的に伝える支援を行った事例に対し、先生より、同じ衣類を着ない事が重要ではなく、最終的にはご本人が自分で着たい衣類を選択できるという事が大事な事であると。
先生の講演の中で、また事例発表の助言の中でも終始、話されていたことは、ご本人さんからの視点で物事を考えるという事、そしてその事がご本人の生活が豊かになる事に繋がる、そして、それこそが私たちが考える支援の基本だという事を学びました。
平成31年2月26日、法人全体の職員研修会が開かれました。
2019-03-04
平成31年2月26日、職員研修会がおんべつ学園で行われ、音別地区、釧路地区の全事業所の職員が参加する研修会となりました。
今回の研修は、初の試みである法人全体での研修会で、内容としては各事業所で実際に行われている支援の内容を発表する「事例発表、検討会」でした。おんべつ学園、共同生活援助事業所はばたき、生活介護事業所あゆみから事例発表を行い、その後グループワークにて意見交換を行っています。
今まで行ってきたことを発表する事、そして他事業所の取り組みをじっくりと聞く事は、日常ではなかなか得られない貴重な時間となり、又、グループワークでは様々な視点から意見を出し合う事が出来、職員一人ひとりが今後支援を行っていく中で視野を広げて支援をしていける良い機会となりました。
研修会「オムツの種類と特性」
2016-06-13
去る5月24日(火)、おんべつ学園3階集会所にて職員研修が行われました。利用者の高齢化対策のシリーズとして、講師に株式会社光洋北海道支社 主任 加藤 祐司氏、コンシェルジュ 大田黒 幸枝氏を招き、「紙オムツの当て方とスキンケア」について講演をして頂きました。
オムツと尿取りパットの構造、正しい当て方やサイズ選びについて、実践を交えながら分かりやすく説明していただきました。
サイズや当て方を適正化することで尿漏れを防いだり着用の不快感や介護者の負担を軽減できることを知り、目から鱗が落ちる思いでした。
グループに分かれて実際にオムツを当てられる体験をした際は、介護される側の気持ちが少し理解することが出来、丁寧な対応が求められると痛感しました。
職員研修「口腔ケアは誤嚥を防ぐ」
2015-07-30
7月25日(土)『口腔ケアは肺炎・窒息・誤嚥を防ぐ』をテーマに、村上歯科口腔外科医院医院長 村上有二先生をお招きし、職員研修を開催いたしました。
当法人の利用者の皆さんの高齢化に伴い、摂食・嚥下障害による誤嚥性肺炎を患う方が増えてきています。今回は、正しい摂食・嚥下法や口腔内のケアについて詳しく説明して頂き、また、すぐに実践できる嚥下に関するトレーニングを指導して頂き、職員のスキルアップに繋がる実りある研修となりました。
当法人の利用者の皆さんの高齢化に伴い、摂食・嚥下障害による誤嚥性肺炎を患う方が増えてきています。今回は、正しい摂食・嚥下法や口腔内のケアについて詳しく説明して頂き、また、すぐに実践できる嚥下に関するトレーニングを指導して頂き、職員のスキルアップに繋がる実りある研修となりました。
各種研修会
研修会のお知らせ (2014-08-18 ・ 127KB) |